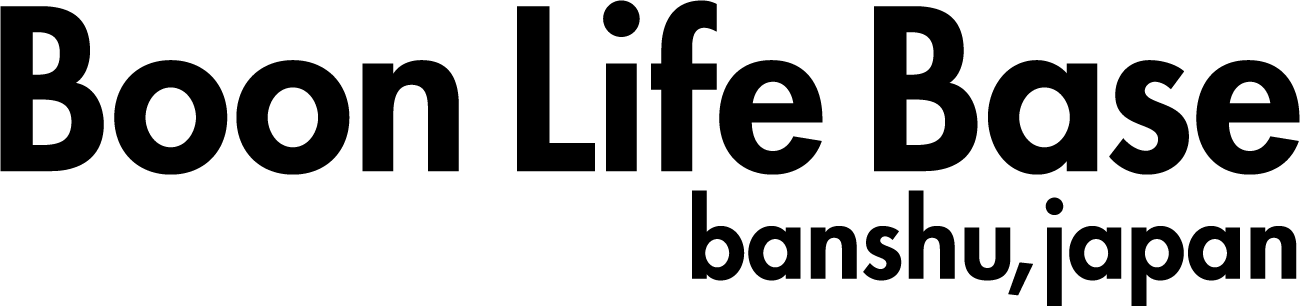播州織とは?
播州織は兵庫県の中央部、播州地区を中心に地場産業として生産されています。
地名から名付けられた播州織は、中国山地に囲まれ、加古川・杉原川・野間川から
流れる超軟水を活用した先染め織物。文字通り、先に糸を染め、染めあがった糸で
生地を織り上げます。糸染め・織り・加工と分業化されており、さまざまな工程を職人の手により、
繋げて完成される織物。色を自由に組み合わせ、多彩な柄や織表現で、
光沢のある色彩と自然な風合いがかもし出される布となります。
播州織の歴史

1792(江戸時代・寛政4年)
西脇生まれの大工、飛田安兵衛が京都西陣織から織物技術を導入したとされる。
1826(江戸時代・文政4年)
地名の播州から”播州織”と謳われる。
江戸時代末期
工場性手工業の段階に達し、産地が形成される。
1866(明治元年)
播州地区の織業家が70戸に達する。当時の染色は藍等の植物染料。
1877(明治10年)
合成化学染料が輸入され、色彩が多様化し、近代化へ。

1923(大正12年)
動力源として電力が普及。この頃、輸出転換の転機が訪れる。
1937(昭和12年)
播州織業界の織機が16,368台に。黄金時代を築く。
1987(昭和62年)
生産のピーク。年間387,769平方メートルを製造。
2000年代〜
分業生産を活かし、多品種、小ロット、短サイクルの需要に応えられるものづくりへ。
2023(令和5年)
生地生産だけであった産地に縫製工場を再設し、製品まで一貫へ。